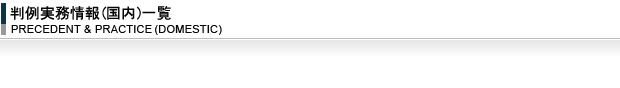
уАРчЯеш▓бщлШшгБуАБф╕Нцнгчл╢ф║ЙуАСуААф╕Нчл╢ц│Х2цЭб1щаЕ14хП╖уБлуВИуВЛцРНхо│ш│ахДЯш▓мф╗╗уБоцЬЙчДбуБохИдцЦнуБлуБКуБДуБжуБпуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБоцийхИйшбМф╜┐уВТф╕Нх┐ЕшжБуБлшРОч╕оуБХуБЫуВЛуБКуБЭуВМуБоцЬЙчДбуВДя╝МхЦ╢ценф╕КуБоф┐бчФиуВТхо│уБХуВМуВЛчл╢ценшАЕуБохИйчЫКуВТч╖ПхРИчЪДуБлшАГцЕоуБЧуБЯф╕КуБзя╝МщБХц│ХцАзуВДцХЕцДПщБОхд▒уБоцЬЙчДбуВТхИдцЦнуБЩуБ╣уБНуБиуБХуВМуБЯф║Лф╛ЛуАВ(х╣│цИР22(уГН)10074уААщЫДуБнуБШщГихУБф║Лф╗╢)
Date.2011х╣┤4цЬИ19цЧе

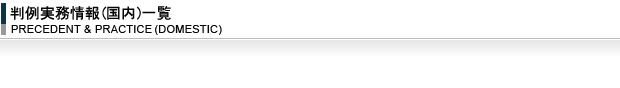
чЯеш▓бщлШшгБх╣│цИР23х╣┤02цЬИ24цЧехИдц▒║уААх╣│цИР22(уГН)10074уААщЫДуБнуБШщГихУБф║Лф╗╢
уГ╗цОзши┤ф║║хЕ╝швлцОзши┤ф║║я╝Ичммя╝СхпйцЬмши┤хОЯхСКуГ╗хПНши┤швлхСКя╝ЙуГЩуВпуГИуГкуГГуВпуВ╣цакх╝Пф╝Ъчд╛я╝Ия╝СхпйхОЯхСКя╝ЙуААхп╛уААшвлцОзши┤ф║║хЕ╝цОзши┤ф║║я╝Ичммя╝СхпйцЬмши┤швлхСКуГ╗хПНши┤хОЯхСКя╝Йцакх╝Пф╝Ъчд╛уГХуВлуВ╡уГпя╝Ия╝СхпйшвлхСКя╝Й
уГ╗я╝СхпйшвлхСКуБоцОзши┤уААф╕АщГишкНхо╣уГ╗ф╕АщГицгДхН┤уАБя╝СхпйхОЯхСКуБоцОзши┤цгДхН┤
уГ╗чЙ╣ши▒ц│Х29цЭб2щаЕуАБф╕Нцнгчл╢ф║ЙщШ▓цнвц│Х2цЭб1щаЕ14хП╖уАБщА▓цнйцАзуАБхо╣цШУцГ│хИ░цАзуАБхЦ╢ценф╕КуБоф┐бчФиуАБф┐бчФицпАцРНя╝ИхЦ╢ценшк╣шмЧя╝ЙуАБшнжхСКуАБщБОхд▒
я╝Ич╡Мч╖пя╝Й
уААя╝СхпйшвлхСКуБпуАБуАМщЫДуБнуБШщГихУБуАНуБочЙ╣ши▒чЩ║цШОя╝ИчЙ╣ши▒чмм3999997хП╖я╝ЙуБочЙ╣ши▒цийшАЕуБзуБВуВЛуАВ
уААя╝СхпйхОЯхСКуБпуАБя╝СхпйшвлхСКуБлхп╛уБЧуАБхОЯхСКшг╜хУБуБош▓йхг▓уБМцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБоф╛╡хо│уБлх╜УуБЯуВЙуБЪуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБлхЯ║уБеуБПх╖оцнвшлЛц▒ВцийуВТцЬЙуБЧуБкуБДуБУуБиуБочв║шкНуБиуАБя╝СхпйшвлхСКуБМя╝СхпйхОЯхСКуБохПЦх╝ХхЕИуБлхп╛уБЧуБжя╝СхпйхОЯхСКуБош▓йхг▓уБЩуВЛхОЯхСКшг╜хУБуБМцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуВТф╛╡хо│уБЩуВЛцЧихСКчЯеуБЧуБЯуБУуБия╝ИцЬмф╗╢хСКчЯешбМчВ║я╝ЙуБМф╕Нчл╢ц│Хя╝ТцЭбя╝СщаЕя╝Ся╝ФхП╖цЙАхоЪуБоф╕Нцнгчл╢ф║ЙуБлшй▓х╜УуБЩуВЛуБиф╕╗х╝╡уБЧуБжуАБцРНхо│ш│ахДЯуВТц▒ВуВБуВЛши┤уБИуВТцЭ▒ф║мхЬ░шгБуБлцПРш╡╖уБЧуБЯуАВ
уААуБУуВМуБлхп╛уБЧуБжуАБя╝СхпйшвлхСКуБпуАБя╝СхпйхОЯхСКуБлхп╛уБЧуАБхОЯхСКшг╜хУБуБош▓йхг▓уБМцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБоф╛╡хо│уБлх╜УуБЯуВЛуБиф╕╗х╝╡уБЧуБжуАБчЙ╣ши▒ц│Хя╝Ця╝ХцЭбя╝СщаЕх╛Мцо╡уБлхЯ║уБеуБПшгЬхДЯщЗСуБКуВИуБ│чЙ╣ши▒цийф╛╡хо│уБоф╕Нц│ХшбМчВ║я╝Иц░Сц│Хя╝Чя╝Ря╝ЩцЭбуАБчЙ╣ши▒ц│Хя╝Ся╝Ря╝ТцЭбя╝ТщаЕя╝ЙуБлхЯ║уБеуБПцРНхо│ш│ахДЯщЗСуВТц▒ВуВБуБжуАБцЭ▒ф║мхЬ░шгБуБлхПНши┤уБЧуБЯуАВ
уААя╝СхпйуБоцЭ▒ф║мхЬ░шгБуБпуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒уБМуАБщА▓цнйцАзуБоцмахжВуБлуВИуВКчДбхК╣уБлуБХуВМуВЛуБ╣уБНуВВуБоуБишкНуВБуВЙуВМуВЛуБЛуВЙуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБлхЯ║уБеуБНцийхИйшбМф╜┐уВТуБЩуВЛуБУуБиуБпуБзуБНуБкуБДуБиуБЧуБжуАБх╖оцнвшлЛц▒Вцийф╕НхнШхЬичв║шкНшлЛц▒ВуВТшкНхо╣уБЧуБЯуАВуБЭуБоф╕АцЦ╣уАБя╝СхпйшвлхСКуБоцЬмф╗╢хСКчЯешбМчВ║уБпуАБф╕Нчл╢ц│Хя╝ТцЭбя╝СщаЕя╝Ся╝ФхП╖уБлшй▓х╜УуБЩуВЛуБиуБЧуБжуАБцРНхо│ш│ахДЯшлЛц▒ВуБоф╕АщГиуВТшкНхо╣уБЧуБЯуАВ
уААцЬмф╗╢уБпуАБуБУуБохИдц▒║уБлф╕НцЬНуБоя╝СхпйхОЯхСКуБКуВИуБ│я╝СхпйшвлхСКуБМуАБчЯеш▓бщлШшгБуБлуБЭуВМуБЮуВМцОзши┤уБЧуБЯф║Лф╗╢уБзуБВуВЛуАВ
я╝Иф║ЙчВ╣я╝Й
уААцЬмф╗╢уБоф╕╗уБкф║ЙчВ╣уБпуАБф╗еф╕ЛуБощАЪуВКуБзуБВуВЛуАВ
уААуГ╗чЙ╣ши▒ц│Х104цЭбуБо3чмм1щаЕуБоцийхИйшбМф╜┐уБохИ╢щЩР
уААуААщА▓цнйцАзцмахжВя╝ИчЙ╣ши▒ц│Хя╝Тя╝ЩцЭбя╝ТщаЕя╝Й
уААуГ╗ф╕Нцнгчл╢ф║Йя╝Иф╕Нчл╢ц│Хя╝ТцЭбя╝СщаЕя╝Ся╝ФхП╖я╝ЙуБоцИРхРжхПКуБ│цРНхо│щбН
я╝ИшгБхИдцЙАуБохИдцЦня╝Й
уААф╕КшиШф║ЙчВ╣уБоуБЖуБбуАБф╕Нчл╢ц│Х2цЭб1щаЕ14хП╖уБоцИРхРжуБлуБдуБДуБжуБпуАБф╗еф╕ЛуБощАЪуВКхИдчд║уБХуВМуБжуБДуВЛуАВ
уААхЕИуБЪуАБя╝СхпйшвлхСКуБоцЬмф╗╢хСКчЯешбМчВ║уБпуАБф╗еф╕ЛуБощАЪуВКуБзуБВуБгуБЯуАВ
уААуГ╗я╝СхпйшвлхСКуБпуАБуГЯуГдуВмуГпщЗСх▒Юш▓йхг▓уБлхп╛уБЧуАБх╣│цИРя╝Ся╝Щх╣┤я╝ШцЬИя╝Тя╝РцЧеф╗ШуБСуБоцЫ╕щЭвуБлуВИуВКуАБхРМчд╛уБМя╝СхпйхОЯхСКуБлш▓йхг▓уБЧуБжуБДуВЛуГСуГпуГ╝уБнуБШя╝ИхОЯхСКшг╜хУБя╝ЙуБМя╝СхпйшвлхСКуБоцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуВТф╛╡хо│уБЧуБжуБДуВЛуБУуБиуБМцШОчЩ╜уБзуБВуВКуАБхОЯхСКшг╜хУБуБошг╜щАауАБш▓йхг▓уБоф╕нцнвуАБхЬих║лхУБуБох╗ГцгДхПКуБ│цРНхо│ш│ахДЯуВТшлЛц▒ВуБЩуВЛхПпшГ╜цАзуБМуБВуВЛцЧиуВТхСКчЯеуБЧуБЯуАВ
уААуГ╗я╝СхпйшвлхСКуБпуАБуГЯуГдуВмуГпхПКуБ│уГЯуГдуВмуГпщЗСх▒Юш▓йхг▓уБлхп╛уБЧуАБх╣│цИРя╝Ся╝Щх╣┤я╝ЩцЬИя╝Ся╝ШцЧеф╗ШуБСуБошнжхСКцЫ╕уБлуВИуВКуАБуГЯуГдуВмуГпуБМшг╜щАауБЧуАБуГЯуГдуВмуГпщЗСх▒Юш▓йхг▓уБМш▓йхг▓уБЧуБжуБДуВЛуГСуГпуГ╝уБнуБШя╝ИхОЯхСКшг╜хУБя╝ЙуБМцЬмф╗╢чЙ╣ши▒чЩ║цШОуБоцКАшбУчЪДчпДхЫ▓уБлх▒ЮуБЩуВЛуВВуБоуБзуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуВТф╛╡хо│уБЩуВЛуВВуБоуБзуБВуВКуАБуБЭуБошг╜щАауАБш▓йхг▓уВТчЫ┤уБбуБлхБЬцнвуБЩуВЛуВИуБЖшнжхСКуБЧуБЯуАВ
уААцЬмф╗╢чЙ╣ши▒уБпуАБхОЯхИдц▒║уБощАЪуВКуАБчДбхК╣хпйхИдуБлуВИуВКчДбхК╣уБлуБХуВМуВЛуБ╣уБНуВВуБоуБзуБВуБгуБЯуБУуБиуБЛуВЙуАБч╡РшлЦуБиуБЧуБжуАБя╝СхпйхОЯхСКуБошбМчВ║уБпцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБоф╛╡хо│шбМчВ║уБлшй▓х╜УуБЧуБкуБЛуБгуБЯуАВуБЭуБоуБЯуВБуАБф╕КшиШуБоя╝СхпйшвлхСКуБлуВИуВЛхСКчЯешбМчВ║уБпуАБч╡РцЮЬчЪДуБлуБпшЩЪхБ╜уБиуБкуБгуБЯуАВ
уААуБЧуБЛуБЧуАБчЯеш▓бщлШшгБуБпуАБуБУуБоуВИуБЖуБкя╝СхпйшвлхСКуБлуВИуВЛхСКчЯешбМчВ║уБпуАБф╕Нчл╢ц│Хя╝ТцЭб1щаЕ14хП╖уБлхЯ║уБеуБПцРНхо│ш│ахДЯш▓мф╗╗уБМуБкуБДуБихИдчд║уБЧуБЯуАВ
уААуАМя╝СхпйшвлхСКуБМцЬЙуБЩуВЛцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБпуАБчЙ╣ши▒х║БуБлуБКуБСуВЛхпйцЯ╗уВТч╡МуБжцЛТч╡╢чРЖчФ▒уВТчЩ║шжЛуБЧуБкуБДуБиуБЧуБжчЙ╣ши▒цЯ╗хоЪуБлшЗ│уБгуБЯуВВуБоуБзуБВуВКя╝ИчЙ╣ши▒ц│Хя╝Хя╝СцЭбя╝ЙуАБчДбхК╣хпйц▒║уБМуБХуВМуБЯуВПуБСуБзуВВуБкуБПуАБф╗ЦцЦ╣уАБхОЯхСКшг╜хУБуБМцЬмф╗╢чЙ╣ши▒чЩ║цШОуБоцКАшбУчЪДчпДхЫ▓уБлх▒ЮуБЩуВЛуБУуБиуБпуАБцШОуВЙуБЛуБзуБВуВКуАБх╜Уф║ЛшАЕщЦУуБлф║ЙуБДуБМуБкуБДуАВуБЭуБЧуБжуАБуГЯуГдуВмуГпхПКуБ│уГЯуГдуВмуГпщЗСх▒Юш▓йхг▓уБпуАБхОЯхСКшг╜хУБуВТшг╜щАаш▓йхг▓уБЩуВЛшАЕуБзуБВуВЛуБЛуВЙуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒уБМчЙ╣ши▒чДбхК╣хпйхИдуБлуВИуВКчДбхК╣уБлуБХуВМуВЛуБ╣уБНуВВуБоуБзуБВуВЛуБкуБйуБоцКЧх╝Бф║ЛчФ▒уБМшкНуВБуВЙуВМуБкуБДха┤хРИуБзуБВуВМуБ░уАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБочЫ┤цОеф╛╡хо│шАЕуБлчЫ╕х╜УуБЩуВЛчлЛха┤уБлуБВуВЛшАЕуБзуБВуВЛуАВуВИуБгуБжуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуВТцЬЙуБЩуВЛя╝СхпйшвлхСКуБпуАБхОЯхСКшг╜хУБуБошг╜щАаш▓йхг▓шбМчВ║уВТшбМуБЖуГЯуГдуВмуГпуВЙуБлхп╛уБЧуБжуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБиуБЧуБжуАБуГЯуГдуВмуГпуВЙуБошбМчВ║уБМцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуВТф╛╡хо│уБЩуВЛуБУуБиуВТхСКчЯеуБЧуБЯуВВуБоуБишзгуБХуВМуВЛуАВ
уГ╗уГ╗уГ╗
уААф╗еф╕КуБоуВИуБЖуБлуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБзуБВуВЛя╝СхпйшвлхСКуБМуАБчЙ╣ши▒чЩ║цШОуВТхоЯцЦ╜уБЩуВЛуГЯуГдуВмуГпуВЙуБлхп╛уБЧуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБоф╛╡хо│уБзуБВуВЛцЧиуБохСКчЯеуВТуБЧуБЯуБУуБиуБлуБдуБДуБжуБпуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБоцийхИйшбМф╜┐уБиуБДуБЖуБ╣уБНуВВуБоуБзуБВуВЛуБиуБУуВНуАБцЬмф╗╢ши┤шиЯуБлуБКуБДуБжуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒уБоцЬЙхК╣цАзуБМф║ЙуВПуВМуАБч╡РцЮЬчЪДуБлцЬмф╗╢чЙ╣ши▒уБМчДбхК╣уБлуБХуВМуВЛуБ╣уБНуВВуБоуБиуБЧуБжцийхИйшбМф╜┐уБМши▒уБХуВМуБкуБДуБиуБХуВМуВЛуБЯуВБуАБя╝СхпйхОЯхСКуБохЦ╢ценф╕КуБоф┐бчФиуВТхо│уБЩуВЛч╡РцЮЬуБиуБкуВЛха┤хРИуБзуБВуБгуБжуВВуАБуБУуБоуВИуБЖуБкха┤хРИуБлуБКуБСуВЛя╝СхпйшвлхСКуБоя╝СхпйхОЯхСКуБлхп╛уБЩуВЛф╕Нчл╢ц│Хя╝ТцЭбя╝СщаЕя╝Ся╝ФхП╖уБлуВИуВЛцРНхо│ш│ахДЯш▓мф╗╗уБоцЬЙчДбуВТцдЬшиОуБЩуВЛуБлх╜УуБЯуБгуБжуБпуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБоцийхИйшбМф╜┐уВТф╕Нх┐ЕшжБуБлшРОч╕оуБХуБЫуВЛуБКуБЭуВМуБоцЬЙчДбуВДуАБхЦ╢ценф╕КуБоф┐бчФиуВТхо│уБХуВМуВЛчл╢ценшАЕуБохИйчЫКуВТч╖ПхРИчЪДуБлшАГцЕоуБЧуБЯф╕КуБзуАБщБХц│ХцАзуВДцХЕцДПщБОхд▒уБоцЬЙчДбуВТхИдцЦнуБЩуБ╣уБНуВВуБоуБишзгуБХуВМуВЛуАВ
уААуБЧуБЛуВЛуБиуБУуВНуАБхЙНшиШшкНхоЪуБоуБиуБКуВКуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒уБочДбхК╣чРЖчФ▒уБлуБдуБДуБжуБпуАБцЬмф╗╢хСКчЯешбМчВ║уБоцЩВчВ╣уБлуБКуБДуБжцШОуВЙуБЛуБкуВВуБоуБзуБпуБкуБПуАБцЦ░шжПцАзцмахжВуБиуБДуБгуБЯцШОчв║уБкуВВуБоуБзуБпуБкуБЛуБгуБЯуБУуБиуБлчЕзуВЙуБЩуБиуАБхЙНшиШшкНхоЪуБочДбхК╣чРЖчФ▒уБлуБдуБДуБжя╝СхпйшвлхСКуБМхНБхИЖуБкцдЬшиОуВТуБЧуБкуБЛуБгуБЯуБиуБДуБЖц│ицДПч╛йхЛЩщБХхПНуВТшкНуВБуВЛуБУуБиуБпуБзуБНуБкуБДуАВуБЭуБЧуБжуАБч╡РцЮЬчЪДуБлуАБцЧнхМЦцИРх╗║цЭРуБохПЦх╝ХуБоуГлуГ╝уГИуБМя╝СхпйхОЯхСКуБЛуВЙя╝СхпйшвлхСКуБлхдЙцЫ┤уБХуВМуБЯуБиуБЧуБжуВВуАБцЬмф╗╢хСКчЯешбМчВ║уБпуАБуБЭуБоцЩВчВ╣уБлуБКуБДуБжуБ┐уВМуБ░уАБхЖЕхо╣уБкуБДуБЧцЕЛцзШуБлуБКуБДуБжуВВчд╛ф╝ЪщАЪх┐╡ф╕КшСЧуБЧуБПф╕НчЫ╕х╜УуБзуБВуВЛуБиуБпуБДуБИуБЪуАБцЬмф╗╢чЙ╣ши▒цийуБлхЯ║уБеуБПцийхИйшбМф╜┐уБочпДхЫ▓уВТщА╕шД▒уБЩуВЛуВВуБоуБиуБ╛уБзуБпуБДуБЖуБУуБиуВВуБзуБНуБкуБДуАВуАН
уААх╛УцЭеуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБМшвлчЦСф╛╡хо│шАЕуБохПЦх╝ХхЕИчнЙуБлшнжхСКчнЙуВТуБЩуВЛшбМчВ║уБпуАБх╛МуБлшгБхИдцЙАчнЙуБзф╛╡хо│ф╕НцИРчлЛуАБчДбхК╣чнЙуБохИдцЦнуБМуБкуБХуВМуБЯха┤хРИуАБхЕ╖ф╜УчЪДуБкф║ЛцГЕчнЙуВТшАГцЕоуБЩуВЛуБУуБиуБкуБПуАБф╕Нчл╢ц│Х2цЭб1щаЕ14хП╖уБоф┐бчФицпАцРНшбМчВ║уБлшй▓х╜УуБЩуВЛуБиуБЧуБЯхИдцЦнуБМуБкуБХуВМуБжуБДуБЯуАВ
уААуБЧуБЛуБЧуАБцЭ▒ф║мхЬ░шгБх╣│цИР13х╣┤9цЬИ20цЧея╝ИчгБц░Чф┐бхП╖шиШщМ▓чФич▓ЙцЬлф║Лф╗╢я╝ЙуБоф║Лф╗╢ф╗ецЭеуАБф╕Нчл╢ц│Х2цЭб1щаЕ14хП╖уБошй▓х╜УцАзхИдцЦнуБлуБКуБДуБжуБпуАБщБХц│ХцАзщШ╗хН┤ф║ЛчФ▒уБоцЬЙчДбуБМцдЬшиОуБХуВМуВЛуВИуБЖуБлуБкуБгуБЯуАВхН│уБбуАБшЩЪхБ╜уБоф║ЛхоЯуБошй▓х╜УцАзуБлуБдуБДуБжуБпуБУуВМуБ╛уБзщАЪуВКхИдцЦнуБЧуАБхдЦх╜вчЪДуБлф┐бчФицпАцРНшбМчВ║уБлшй▓х╜УуБЩуВЛха┤хРИуБзуВВуАБчЙ╣ши▒цийшАЕуБлуВИуВЛшнжхСКчнЙуБохСКчЯешбМчВ║уБМцнгх╜УуБкцийхИйшбМф╜┐уБоф╕АчТ░уБиуБ┐уБкуБХуВМуВЛха┤хРИуБпуАБуБЭуБощБХц│ХцАзуБМщШ╗хН┤уБХуВМуВЛуБиуБЩуВЛуВВуБоуБзуБВуВЛуАВ
уААцЬмф╗╢уБлуБдуБДуБжуБпуАБя╝СхпйшвлхСКуБлуВИуВЛхСКчЯешбМчВ║уБМч╡РцЮЬчЪДуБлшЩЪхБ╜уБиуБкуБгуБЯуБМуАБхСКчЯеуБЧуБЯчЫ╕цЙЛуБМуАБхОЯхСКшг╜хУБуБошг╜щАаш▓йхг▓хЕГуБзуБВуБгуБжчЫ┤цОеф╛╡хо│шАЕуБочлЛха┤уБлуБВуВЛшАЕуБзуБВуВКуАБхСКчЯеуБохЖЕхо╣уВДцЕЛцзШуБлуБКуБДуБжуВВчд╛ф╝ЪчЪДуБлф╕НчЫ╕х╜УуБиуБ╛уБзуБпуБДуБИуБкуБДуБихИдцЦнуБХуВМуБжуБДуВЛуАВхН│уБбуАБцЬмф╗╢уБлуБКуБДуБжуВВуАБщБХц│ХцАзщШ╗хН┤ф║ЛчФ▒уБохнШхЬиуБМшВпхоЪуБХуВМуБЯч╡РцЮЬуАБ2цЭб1щаЕ14хП╖уБлхЯ║уБеуБПцРНхо│ш│ахДЯш▓мф╗╗уБМуБкуБДуБиуБХуВМуБЯуВВуБоуБзуБВуВЛуАВ
уААх░ЪуАБщБХц│ХцАзщШ╗хН┤ф║ЛчФ▒уВТцдЬшиОуБЧуБЯшгБхИдф╛ЛуБиуБЧуБжуБпуАБф╗ЦуБлчЯеш▓бщлШшгБх╣│цИР16х╣┤8цЬИ31цЧея╝ИцР║х╕пщЫ╗шй▒ф║Лф╗╢я╝ЙуАБчЯеш▓бщлШшгБх╣│цИР18х╣┤6цЬИ26цЧея╝Их║ГхСКуГХуВгуГлуГаф║Лф╗╢я╝ЙуБкуБйуБМуБВуВЛуАВ
я╝ИхИдц▒║цЦЗя╝ЙуААhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225144812.pdf