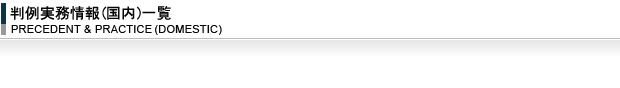
пјҲзҹҘиІЎй«ҳиЈҒгҖҒзү№иЁұпјүгҖҖйҖІжӯ©жҖ§гӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе…ҲиЎҢжҠҖиЎ“гҒӢгӮүеҮәзҷәгҒ—гҒҰеҪ“и©ІзҷәжҳҺгҒ®зӣёйҒ•зӮ№гҒ«дҝӮгӮӢж§ӢжҲҗгҒ«еҲ°йҒ”гҒ§гҒҚгӮӢи©ҰгҒҝгӮ’гҒ—гҒҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶжҺЁжё¬гҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒ®гҒҝгҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®ж§ӢжҲҗгҒ«еҲ°йҒ”гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒ—гҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ®зӨәе”ҶзӯүгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҖе№іжҲҗ22(иЎҢгӮұ)10187
Date.2011е№ҙ1жңҲ18ж—Ҙ

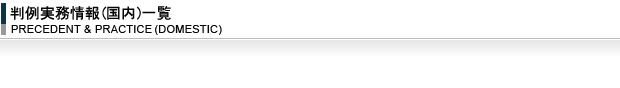
е№іжҲҗ22(иЎҢгӮұ)10187гҖҖдјёзё®еҸҜж’“з®ЎгҒ®з§»еӢ•иҰҸеҲ¶иЈ…зҪ®дәӢ件гҖҖе№іжҲҗ22е№ҙ12жңҲ28ж—ҘеҲӨжұә
гғ»и«ӢжұӮиӘҚе®№
гғ»гӮігӮ№гғўе·Ҙж©ҹж ӘејҸдјҡзӨҫгҖҖеҜҫгҖҖзү№иЁұеәҒй•·е®ҳ
гғ»зү№иЁұжі•29жқЎ2й …гҖҒйҖІжӯ©жҖ§гҖҒе®№жҳ“жғіеҲ°жҖ§
пјҲзөҢз·Ҝпјү
гҖҖеҺҹе‘ҠгҒҜгҖҒгҖҢдјёзё®еҸҜж’“з®ЎгҒ®з§»еӢ•иҰҸеҲ¶иЈ…зҪ®гҖҚгҒ®зҷәжҳҺгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзү№иЁұеҮәйЎҳпјҲзү№йЎҳпј’пјҗпјҗпј“пјҚпј‘пј’пјҗпј“пј“пј’еҸ·гҖҒзү№й–Ӣпј’пјҗпјҗпј”пјҚпј“пј’пј”пј—пј–пјҷеҸ·пјүгӮ’гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҜ©жҹ»е®ҳгҒҜжӢ’зө¶жҹ»е®ҡгӮ’гҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«дёҚжңҚгҒ®еҺҹе‘ҠгҒҜгҖҒжӢ’зө¶жҹ»е®ҡдёҚжңҚеҜ©еҲӨпјҲдёҚжңҚпј’пјҗпјҗпјҷпјҚпј•пј“пј–пј“еҸ·дәӢ件пјүгӮ’и«ӢжұӮгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзү№иЁұеәҒгҒҜгҖҒйҖІжӯ©жҖ§гҒ®ж¬ еҰӮгӮ’зҗҶз”ұгҒ«жӢ’зө¶еҜ©жұәгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮжң¬д»¶гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҜ©жұәгҒ®еҸ–ж¶ҲгҒ—гӮ’жұӮгӮҒгҒҰеҺҹе‘ҠгҒҢзҹҘиІЎй«ҳиЈҒгҒ«иЁҙгҒҲгӮ’жҸҗиө·гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒҠгӮҲгҒіеј•з”ЁзҷәжҳҺпјү
гҖҖжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҗи«ӢжұӮй …пј‘гҖ‘
гҖҖжөҒдҪ“ијёйҖҒз®ЎгҒ®йҖ”дёӯгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢдёҖеҜҫгҒ®еҸҜж’“з¶ҷжүӢйғЁгҒӢгӮүжҲҗгӮӢдјёзё®еҸҜж’“з®ЎгҒ®з§»еӢ•иҰҸеҲ¶иЈ…зҪ®гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒ
еүҚиЁҳдёҖеҜҫгҒ®з¶ҷжүӢйғЁгҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еӨ–е‘ЁгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹеҸ–д»ҳзүҮгӮ’жңүгҒ—гҖҒдә’гҒ„гҒ«ж‘әеӢ•дё”гҒӨеҜҶе°ҒеҸҜиғҪгҒ«ж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҖҒеүҚиЁҳдёЎз¶ҷжүӢйғЁй–“гҒ«гҒҜгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгҒҢе‘Ёж–№еҗ‘гҒ«еүҚиЁҳеҸ–д»ҳзүҮгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰиӨҮж•°жһ¶ж©ӢгҒ•гӮҢгҖҒдёЎеҸ–д»ҳзүҮгҒ®гҒқгӮҢгҒһгӮҢеҶ…еӨ–гҒ«й…ҚиЁӯгҒ—гҒҹдёҖеҜҫгҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒ«гӮҲгӮҠеүҚиЁҳгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгҒҢеҸ–д»ҳзүҮй–“гҒ«еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒ
гҖҖеүҚиЁҳеҸ–д»ҳзүҮгҒ®еӨ–еҒҙгҒ«й…ҚиЁӯгҒ—гҒҹдёҖж–№гҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒҜеүҚиЁҳгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүз«ҜйғЁгҒ®гғҚгӮёйғЁгҒ«иһәзқҖгҒ•гӮҢгҖҒе…ӯи§’гғҠгғғгғҲгҒЁе…ұгҒ«йҮҚгҒӯгҒҰиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢзҗғйқўгғҠгғғгғҲгҒӢгӮүжҲҗгӮӢгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒеүҚиЁҳзҗғйқўгғҠгғғгғҲгҒЁеүҚиЁҳеҸ–д»ҳзүҮгҒЁгҒ®й–“гҒ«зҗғйқўеә§йҮ‘гӮ’д»ӢеңЁгҒ•гҒӣгҖҒдә’гҒ„гҒ®еҮ№еҮёзҗғйқўйғЁгҒ§ж‘әеӢ•гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁе…ұгҒ«гҖҒеүҚиЁҳеҸ–д»ҳзүҮгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«й…ҚиЁӯгҒ—гҒҹд»–ж–№гҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒҜеүҚиЁҳгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүз«ҜйғЁгҒ®гғҚгӮёйғЁгҒ«иһәжҢҝгҒ•гӮҢгӮӢгғҠгғғгғҲгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒеүҚиЁҳжөҒдҪ“ијёйҖҒз®ЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰең§зё®ж–№еҗ‘гҒ«гҖҒгҒӢгҒӨеүҚиЁҳгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгӮ’еӨүеҪўгҒ•гҒӣгӮӢз•°еёёиҚ·йҮҚгҒҢдҪңз”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚеүҚиЁҳгғҠгғғгғҲгҒ®гғҚгӮёйғЁгҒ®еӨүеҪўгҒҫгҒҹгҒҜз ҙеЈҠгҒ«гӮҲгӮҠеүҚиЁҳз•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зү№еҫҙгҒЁгҒҷгӮӢдјёзё®еҸҜж’“з®ЎгҒ®з§»еӢ•иҰҸеҲ¶иЈ…зҪ®гҖӮ
гҖҖеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒҜд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖгӮ№гғӘгғјгғ–пј’гҒЁдәҢеҖӢгҒ®гӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“гҒЁгҒҢзҗғйқўгғӘгғігӮ°жқҗпј‘гӮ’д»ӢгҒ—гҒҰдјёзё®еҸҜиғҪгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒзӣёеҜҫжҸәеӢ•еҸҜиғҪгҒ«йҖЈзөҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж°ҙйҒ“з”ЁгҒ®дјёзё®еҸҜж’“з®Ўз¶ҷжүӢпјЎгҒ®дәҢеҖӢгҒ®гӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“гҒ©гҒҶгҒ—гҒ®зӣёеҜҫ移еӢ•гӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢйҳ»жӯўжүӢж®өпјўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒ
гҖҖгӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“еҗ„гҖ…гҒ®еӨ–е‘ЁеҒҙгҒ«иӨҮж•°еҖӢгҒ®гғңгӮ№пј‘пј’гӮ’зӯүй–“йҡ”гҒ§з’°зҠ¶гҒ«й…ҚзҪ®гҒ—гҒҰдёҖдҪ“еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҗғйқўгғӘгғігӮ°жқҗпј‘гҒЁгӮ№гғӘгғјгғ–пј’гҒЁгҒ®й–“еҸҠгҒізҗғйқўгғӘгғігӮ°жқҗпј‘гҒЁгӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“гҒЁгҒ®й–“гҒ®еҗ„гҖ…гҒ«гӮҙгғ иЈҪгҒ®гӮ·гғјгғ«гғӘгғігӮ°пјҳгҖҒпјҷгҒҢеөҢгӮҒиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдәҢеҖӢгҒ®гӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“гҒ®гғңгӮ№пј‘пј’гҒ©гҒҶгҒ—гҒ«дәҳгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“гҒ©гҒҶгҒ—гӮ’йҖЈзөҗгҒҷгӮӢйҖЈзөҗйғЁжқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®йӣ„гҒӯгҒҳпј‘пј”гҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйӢјиЈҪгғӯгғғгғүпј‘пј“гӮ’жҢҝйҖҡгҒ—гҖҒгғңгӮ№пј‘пј’гҒ®еҗ„гҖ…гҒЁгғӯгғғгғүпј‘пј“гҒЁгӮ’дәҢеҖӢгҒ®гғҠгғғгғҲпј‘пј•гҒ§з· гӮҒд»ҳгҒ‘еӣәе®ҡгҒ—гҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдјёзё®еҸҜж’“з®Ўз¶ҷжүӢпјЎгҒ®дәҢеҖӢгҒ®гӮұгғјгӮ·гғігӮ°з®Ўпј“гҒ©гҒҶгҒ—гҒ®зӣёеҜҫ移еӢ•гӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢйҳ»жӯўжүӢж®өпјў
пјҲжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒЁеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒ®еҜҫжҜ”пјү
гҖҖжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒЁеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒ®зӣёйҒ•зӮ№гҒҜпј’гҒӨгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒдёӢиЁҳзӣёйҒ•зӮ№пј’гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒ®ж§ӢжҲҗгҒ®е®№жҳ“жғіеҲ°жҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пј»зӣёйҒ•зӮ№пј‘пјҪ
гҖҖеҸ–д»ҳзүҮгҒ®еӨ–еҒҙгҒ«й…ҚиЁӯгҒ—гҒҹдёҖж–№гҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒҢгҖҒжң¬йЎҳиЈңжӯЈзҷәжҳҺгҒ§гҒҜгҖҒгҖҺе…ӯи§’гғҠгғғгғҲгҒЁе…ұгҒ«йҮҚгҒӯгҒҰиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢзҗғйқўгғҠгғғгғҲгҒӢгӮүжҲҗгӮӢгғҖгғ–гғ«гғҠгғғгғҲгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒеүҚиЁҳзҗғйқўгғҠгғғгғҲгҒЁеүҚиЁҳеҸ–д»ҳзүҮгҒЁгҒ®й–“гҒ«зҗғйқўеә§йҮ‘гӮ’д»ӢеңЁгҒ•гҒӣгҖҒдә’гҒ„гҒ®еҮ№еҮёзҗғйқўйғЁгҒ§ж‘әеӢ•гҒ•гҒӣгӮӢгҖҸгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒ§гҒҜгҖҒпјҲеҚҳдёҖгҒ®пјүгҖҺгғҠгғғгғҲпј‘пј•гҖҸгҒ§гҒӮгӮӢзӮ№гҖӮ
пј»зӣёйҒ•зӮ№пј’пјҪ
гҖҖеҸ–д»ҳзүҮгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«й…ҚиЁӯгҒ—гҒҹд»–ж–№гҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒҢгҖҒжң¬йЎҳиЈңжӯЈзҷәжҳҺгҒ§гҒҜгҖҒгҖҺеүҚиЁҳжөҒдҪ“ијёйҖҒз®ЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰең§зё®ж–№еҗ‘гҒ«гҖҒгҒӢгҒӨеүҚиЁҳгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгӮ’еӨүеҪўгҒ•гҒӣгӮӢз•°еёёиҚ·йҮҚгҒҢдҪңз”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚеүҚиЁҳгғҠгғғгғҲгҒ®гғҚгӮёйғЁгҒ®еӨүеҪўгҒҫгҒҹгҒҜз ҙеЈҠгҒ«гӮҲгӮҠеүҚиЁҳз•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҖҸгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒ§гҒҜгҖҒпјҲйҖҡеёёгҒ®пјүгҖҺгғҠгғғгғҲпј‘пј•гҖҸгҒ§гҒӮгӮӢзӮ№гҖӮ
пјҲдәүзӮ№пјү
гҖҖдәүзӮ№гҒҜгҖҒеҸ–д»ҳзүҮгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«й…ҚиЁӯгҒ—гҒҹдҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒ®гҖҢгғҠгғғгғҲпј‘пј•гҖҚгҒ«д»ЈгҒҲгҒҰгҖҒеј•з”ЁдҫӢпј’иЁҳијүгҒ®дҪҺеј·еәҰгҒ®гҖҢгғҠгғғгғҲпј’пј–пјЎгҖҚгӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢеүҚиЁҳжөҒдҪ“ијёйҖҒз®ЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰең§зё®ж–№еҗ‘гҒ«гҖҒгҒӢгҒӨеүҚиЁҳгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгӮ’еӨүеҪўгҒ•гҒӣгӮӢз•°еёёиҚ·йҮҚгҒҢдҪңз”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚеүҚиЁҳгғҠгғғгғҲгҒ®гғҚгӮёйғЁгҒ®еӨүеҪўгҒҫгҒҹгҒҜз ҙеЈҠгҒ«гӮҲгӮҠеүҚиЁҳз•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ®жң¬йЎҳиЈңжӯЈзҷәжҳҺгҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒ«дҝӮгӮӢж§ӢжҲҗпјҲзӣёйҒ•зӮ№пј’гҒ«дҝӮгӮӢж§ӢжҲҗпјүгҒ«жғіеҲ°гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҪ“жҘӯиҖ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе®№жҳ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨж–ӯпјү
гҖҖеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒҜгҖҒгҒқгҒ®и„ҶејұйғЁгӮ’иЈңеј·гҒҷгӮӢиЈңеј·жүӢж®өгҒҢгҖҒеҪ“и©Іи„ҶејұйғЁгӮ’иЈңеј·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиЈңеј·зҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүгҖҒеҪ“и©Іи„ҶејұйғЁгҒ®иЈңеј·гӮ’и§ЈйҷӨгҒҷгӮӢиЈңеј·и§ЈйҷӨзҠ¶ж…ӢгҒёеҲҮжҸӣж“ҚдҪңеҸҜиғҪгҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйҒӢжҗ¬дёӯгӮ„й…Қз®Ўж–Ҫе·ҘдёӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиЈңеј·зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒй…Қз®Ўзӣёдә’гҒ®зӣёеҜҫ移еӢ•гӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒж–Ҫе·ҘеҫҢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиЈңеј·и§ЈйҷӨзҠ¶ж…ӢгҒёеҲҮгӮҠжҸӣгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгӮҸгҒҡгҒӢгҒӘиЎқж’ғеҠӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮгҒқгҒ®и„ҶејұйғЁпјҲе®ҹж–ҪдҫӢгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜеҲҮж¬ йғЁпј‘пј–гӮ’жңүгҒҷгӮӢгғӯгғғгғүпј‘пј“пјүгҒҢз ҙеЈҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ–еҠӣгӮ’еҗёеҸҺгҒ•гҒӣгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖдёҖж–№гҖҒжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒҜгҖҒгҖҢеҸ–д»ҳзүҮгҒ®еҶ…еҒҙгҒ«й…ҚиЁӯгҒ•гӮҢгӮӢдҝӮеҗҲйғЁжқҗпјҲгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүз«ҜйғЁгҒ®гғҚгӮёйғЁгҒ«иһәжҢҝгҒ•гӮҢгӮӢгғҠгғғгғҲпј“пјҗпјүгҒҢең§зё®ж–№еҗ‘гҒ®з•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒеҶ…еҒҙгҒ®дҝӮеҗҲйғЁжқҗгҒ®гҒҝгӮ’еӨүеҪўеҸҲгҒҜз ҙжҗҚгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒқгҒ®з•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҗёеҸҺгҒ—гҒҰгҖҒгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гҒҢеӨүеҪўеҸҲгҒҜз ҙжҗҚгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҖҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҚігҒЎгҖҒжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒҜгҖҒеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒЁз•°гҒӘгӮҠгҖҒгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгҒ«и„ҶејұйғЁгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹдёҠгҖҒи„ҶејұйғЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒиЈңеј·зҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүиЈңеј·и§ЈйҷӨзҠ¶ж…ӢгҒёгҒ®еҲҮжҸӣж“ҚдҪңгӮ’еҸҜиғҪгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ®ж§ӢжҲҗгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҖҒжң¬д»¶зҷәжҳҺгҒЁеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒЁгҒҜгҖҒзҷәжҳҺгҒ®жҠҖиЎ“зҡ„жҖқжғігҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҢеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиЈңеј·зҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүиЈңеј·и§ЈйҷӨзҠ¶ж…ӢгҒёгҒ®еҲҮжҸӣж“ҚдҪңгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ®зү№еҫҙзҡ„ж§ӢжҲҗгӮ’жңүгҒ—гҖҒй…Қз®Ўж–Ҫе·ҘеҫҢгҒ®иЈңеј·и§ЈйҷӨзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒз•°еёёиҚ·йҮҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гӮ’з ҙеЈҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒй…Қз®ЎгҒ®зӣёеҜҫ移еӢ•гӮ’зўәдҝқгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжң¬йЎҳиЈңжӯЈзҷәжҳҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүгӮ’иЈңеј·гҒҷгӮӢжүӢж®өгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®иЁҳијүгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйҒӢжҗ¬жҷӮеҸҠгҒій…Қз®Ўж–Ҫе·ҘеҫҢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒз•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҸ–д»ҳзүҮеҶ…еҒҙгҒ®дҪҺеј·еәҰгғҠгғғгғҲгҒ®еӨ–еҠӣеҗёеҸҺж©ҹиғҪгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гҒ®з ҙжҗҚзӯүгҒҜйҳІжӯўгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®з¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгҒҹгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гҒ®еӨ–еҠӣеҗёеҸҺж©ҹиғҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒжӣҙгҒӘгӮӢз•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдјёзё®еҸҜж’“з®ЎеҸҲгҒҜй…Қз®ЎиҮӘдҪ“гҒ®жҗҚеӮ·гӮ’йҳІжӯўгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒЁжң¬йЎҳиЈңжӯЈзҷәжҳҺгҒЁгҒҜгҖҒзҷәжҳҺгҒ®жҠҖиЎ“зҡ„жҖқжғігҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎзҷәжҳҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи§ЈжұәиӘІйЎҢеҸҠгҒіиӘІйЎҢи§ЈжұәжүӢж®өгӮ’з•°гҒ«гҒҷгӮӢгҖӮгҖҚ
гҖҖгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгҖҢгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲең°дёӯгҒ«еҹӢиЁӯгҒҷгӮӢжөҒдҪ“ијёйҖҒз®ЎгӮ„з®Ўз¶ҷжүӢзӯүгҒ«гҒҜең°йңҮгӮ„ең°зӣӨжІҲдёӢгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүеҪўгӮ„з ҙжҗҚгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷгӮҲгҒҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒӘең§зё®еҠӣгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҜҫеҝңгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиӘІйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰе‘ЁзҹҘгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒдҪҺеј·еәҰгғҠгғғгғҲгҒ«дҝӮгӮӢжҠҖиЎ“зҡ„дәӢй …гҒҢе‘ЁзҹҘгҒ®жҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеј•з”ЁдҫӢпјҲеҲҠиЎҢзү©пј‘пјүгҒ«гҖҒеҜ©жұәгҒҢеј•з”ЁгҒ—гҒҹе…ҲиЎҢжҠҖиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒӢгӮүеҮәзҷәгҒ—гҒҰзӣёйҒ•зӮ№пј’гҒ«дҝӮгӮӢжң¬йЎҳиЈңжӯЈзҷәжҳҺгҒ®ж§ӢжҲҗгҒ«еҲ°йҒ”гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒ—гҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӨәе”ҶзӯүгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҖҚгҒЁеҲӨзӨәгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖдёҖж–№гҖҒиў«е‘ҠгҒҜгҖҒеј•з”ЁдҫӢпј‘гҒ«гҒҜгҖҒгҖҢзӯ’зҠ¶дҪ“гҒ©гҒҶгҒ—гӮ’зӣёеҜҫ移еӢ•гҒ•гҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеӨ–еҠӣгҒ§з ҙеЈҠеҸҜиғҪгҒӘи„ҶејұйғЁгҒҜгҖҒйҳ»жӯўжүӢж®өгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢйғЁжқҗгҒ®дёҖйғЁгӮ’д»–гҒ®йғЁжқҗгӮҲгӮҠгӮӮеј·еәҰзҡ„гҒ«ејұгҒ„жқҗж–ҷгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҰж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҖҚпјҲгҖҗпјҗпјҗпј”пјҗгҖ‘пјүзӯүгҒЁгҒ®иЁҳијүгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®иЁҳијүеҶ…е®№гӮ’ж №жӢ гҒ«гҖҒгҖҢйҳ»жӯўжүӢж®өгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢдёҠиЁҳпј“зЁ®гҒ®йғЁжқҗгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢгғңгӮ№пј‘пј’гҖҚгҖҒгҖҢйӢјиЈҪгғӯгғғгғүпј‘пј“гҖҚеҸҠгҒігҖҢдәҢеҖӢгҒ®гғҠгғғгғҲпј‘пј•гҖҚгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮ’и„ҶејұйғЁгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гҒҶгҒЎгҖҢдәҢеҖӢгҒ®гғҠгғғгғҲпј‘пј•гҖҚгҒ®жӣҙгҒ«еҶ…еҒҙгҒ®гғҠгғғгғҲпј‘гҒӨгӮ’и„ҶејұйғЁгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣҙжҺҘзӨәе”ҶгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҲҠиЎҢзү©пј’гҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹи„ҶејұйғЁгҒ®ж§ӢжҲҗгӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®йҳ»е®іиҰҒеӣ гҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁдё»ејөгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҹҘиІЎй«ҳиЈҒгҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®иў«е‘ҠгҒ®дё»ејөгҒҜжҺЎз”ЁгҒ®йҷҗгӮҠгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢеј•з”ЁзҷәжҳҺгҒҜгҖҒиЈңеј·зҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүиЈңеј·и§ЈйҷӨзҠ¶ж…ӢгҒёгҒ®еҲҮжҸӣж“ҚдҪңгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶ第1гҒ®зү№еҫҙзҡ„ж§ӢжҲҗгӮ’жңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒй…Қз®Ўж–Ҫе·ҘеҫҢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиЎқж’ғеҠӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гӮҝгӮӨгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гӮ’з ҙеЈҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒй…Қз®ЎгҒ®зӣёдә’移еӢ•гӮ’иҮӘз”ұгҒ«гҒ•гҒӣгӮӢзҷәжҳҺгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒжң¬йЎҳзҷәжҳҺгҒҜгҖҒиЈңеј·зҠ¶ж…ӢгҒ®еҲҮжҸӣж“ҚдҪңгҒ®ж§ӢжҲҗгӮ’жңүгҒ•гҒҡгҖҒгӮҝгӮӨгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гҒҢдёҖе®ҡзҜ„еӣІеҶ…гҒ®з•°еёёиҚ·йҮҚгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгӮӮз ҙжҗҚгҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’и§ЈжұәиӘІйЎҢгҒЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒдёЎиҖ…гҒҜгҖҒзҷәжҳҺгҒ®и§ЈжұәиӘІйЎҢгҒ®иЁӯе®ҡеҸҠгҒіи§ЈжұәжүӢж®өгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҠҖиЎ“жҖқжғігӮ’з•°гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮеҲҠиЎҢзү©пј‘гҒ®е®ҹж–ҪдҫӢгҒ«гҒҜгҖҒеҲҮж¬ йғЁпј‘пј–гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғӯгғғгғүпј‘пј“иҮӘдҪ“гӮ’е®№жҳ“гҒ«з ҙеЈҠгҒ•гҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒй…Қз®ЎгҒ©гҒҶгҒ—гҒҢиҮӘз”ұгҒ«зӣёеҜҫ移еӢ•гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢзҷәжҳҺгҒ®гҒҝгҒҢй–ӢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«з…§гӮүгҒҷгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгғӯгғғгғүиҮӘдҪ“гӮ’з ҙеЈҠгҒ•гҒӣгӮӢжҠҖиЎ“зҡ„жҖқжғігҒЁзӣёеҸҚгҒҷгӮӢзӣ®зҡ„гҒ§и„ҶејұйғЁгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢжҠҖиЎ“зҡ„дәӢй …гҒ®й–ӢзӨәгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁи§ЈгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеҗҲзҗҶзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒиў«е‘ҠгҒ®дё»ејөгҒ«дҝӮгӮӢж®өиҗҪгҖҗпјҗпјҗпј”пјҗгҖ‘гҒ®иЁҳијүгҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®и§ЈжұәиӘІйЎҢеҸҠгҒіи§ЈжұәжүӢж®өгҒ®зҜ„еӣІгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢгғӯгғғгғүгҒ«еҲҮж¬ йғЁпј‘пј–гӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒйҳ»жӯўжүӢж®өгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгғӯгғғгғүгҒ®дёҖйғЁгӮ’еј·еәҰзҡ„гҒ«ејұгҒ„жқҗж–ҷгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§и„ҶејұйғЁгҒ®йғЁеҲҶгӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҠҖиЎ“гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ«жӯўгҒҫгӮҠгҖҒеҲҠиЎҢзү©пј‘гҒ«й–ӢзӨәгҒ•гӮҢгҒҹе…ЁдҪ“гҒ®и¶Јж—ЁгҒЁйӣўгӮҢгҒҰгҖҒгғӯгғғгғүд»ҘеӨ–гҒ®йғЁеҲҶгҒ«и„ҶејұйғЁгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢжҠҖиЎ“гӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
гҖҖзү№иЁұжі•пј’пјҷжқЎпј’й …гҒёгҒ®и©ІеҪ“жҖ§гӮ’иӮҜе®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒе…ҲиЎҢжҠҖиЎ“гҒӢгӮүеҮәзҷәгҒ—гҒҰеҪ“и©ІзҷәжҳҺгҒ®зӣёйҒ•зӮ№гҒ«дҝӮгӮӢж§ӢжҲҗгҒ«еҲ°йҒ”гҒ§гҒҚгӮӢи©ҰгҒҝгӮ’гҒ—гҒҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶжҺЁжё¬гҒҢжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҒ®гҒҝгҒ§гҒҜеҚҒеҲҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҪ“и©ІзҷәжҳҺгҒ®зӣёйҒ•зӮ№гҒ«дҝӮгӮӢж§ӢжҲҗгҒ«еҲ°йҒ”гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒ—гҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ®зӨәе”ҶзӯүгҒ®еӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒеҲҠиЎҢзү©пј‘гҒ®ж®өиҗҪгҖҗпјҗпјҗпј”пјҗгҖ‘гҒ®иЁҳијүгҒҜгҖҒеҲҠиЎҢзү©пј’гҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҹжҠҖиЎ“гӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢзӣёйҒ•зӮ№гҒ«дҝӮгӮӢж§ӢжҲҗгҒ«еҲ°йҒ”гҒ—гҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ®зӨәе”ҶзӯүгҖҚгӮ’еҗ«гӮҖиЁҳијүгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮгҖҚ
гҖҖгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒжң¬д»¶гҒ«ж–јгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҜ©жұәгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзӣёйҒ•зӮ№пј’гҒ«й–ўгҒҷгӮӢж§ӢжҲҗгҒ®е®№жҳ“жғіеҲ°жҖ§гҒ®еҲӨж–ӯгҒ«гҒҜиӘӨгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҪ“и©ІеҜ©жұәгӮ’еҸ–гӮҠж¶ҲгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖ欧е·һгҒ§зўәз«ӢгҒ—гҒҹгӮұгғјгӮ№гғӯгғјгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢcould-wouldгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒҜгҖҒеҪ“жҘӯиҖ…гҒҢжңҖгӮӮиҝ‘гҒ„еҫ“жқҘжҠҖиЎ“гҒӢгӮүжң¬йЎҳзҷәжҳҺгҒ«еҲ°йҒ”гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶпјҲcouldпјүгҒӢеҗҰгҒӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҪ“жҘӯиҖ…гҒҢе®ўиҰізҡ„иӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжңҹеҫ…гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒқгӮҢгӮ’гҒ—гҒҹгҒ гӮҚгҒҶпјҲwouldпјүгҒӢеҗҰгҒӢгӮ’еҹәжә–гҒ«гҒ—гҒҰйҖІжӯ©жҖ§гҒ®жңүз„ЎгӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖжң¬д»¶гҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®дёӢз·ҡйғЁгҒ«гҒӮгӮӢйҖҡгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®could-wouldгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’гҒ•гӮүгҒ«дёҖжӯ©йҖІгӮҒгҖҒгҖҢгҒ—гҒҹгҒҜгҒҡгҒ§гҒӮгӮӢ(should)гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ¬гғҷгғ«гҒҫгҒ§зӨәе”ҶзӯүгҒ®еӯҳеңЁгӮ’жұӮгӮҒгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨж–ӯжүӢжі•гҒҜгҖҒзҹҘиІЎй«ҳиЈҒ第3йғЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе№іжҲҗ20пјҲиЎҢгӮұпјү10096пјҲеӣһи·ҜжҺҘз¶ҡз”ЁйғЁжқҗдәӢ件пјүгҒ§жңҖеҲқгҒ«зӨәгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®жүӢжі•гҒ«гӮҲгӮӢе®№жҳ“жғіеҲ°жҖ§гҒ®еҲӨж–ӯгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«еӨҡж•°гҒ«гҒ®гҒјгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒе№іжҲҗ20пјҲиЎҢгӮұпјү10153гҖҒе№іжҲҗ20пјҲиЎҢгӮұпјү10261гҖҒе№іжҲҗ21пјҲиЎҢгӮұпјү10223гҖҒе№іжҲҗ21пјҲиЎҢгӮұпјү10268гҖҒе№іжҲҗ21пјҲиЎҢгӮұпјү10293гҖҒе№іжҲҗ21пјҲиЎҢгӮұпјү10036гҒӘгҒ©пјүгҖӮ
пјҲеҲӨжұәж–ҮпјүгҖҖhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228153609.pdf